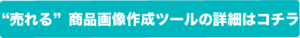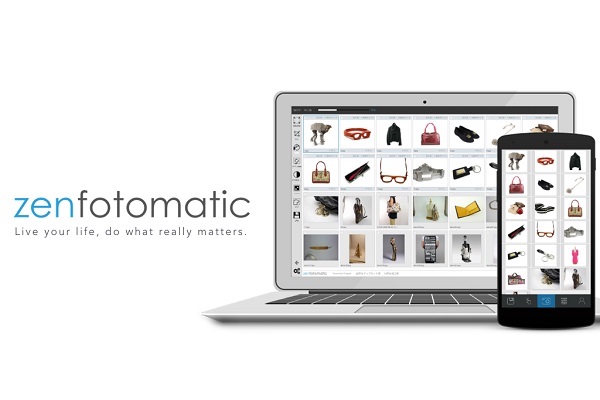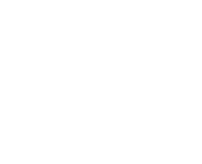立ち上げたECが「ネットショップの皮を被ったシステム屋」に
私はもともと複数のインポートアパレルブランドを取り扱う商社のSE(システムエンジニア)でした。

ネットショップでなら、これまで培ったITスキルを活かしてうまくやれると思い、取りあえず前職でかかわったブランド品を商材として独立したのでした。そう。取り扱う商材のことを二の次にしていたのです。
ふたを開けてみると、自分で仕入れた商材がことごとく売れません。まぁそれもそうでしょう。ファッション業界にいたとは言え、所詮は間接部門のシステム屋です。それでも、売上が無いと生活が成り立ちませんので方法を変えました。
まずは仕入れを受注発注型に変更しました。
仕入先各社の在庫データを日々取得し、品番ベースでの動きを数値化して傾向を把握します。売れ筋は競合店の価格を調べて、少々赤字でも最安値ラインで値付けし、これを広告代わりに運用しました。
ある程度の数が売れてレビューが溜まると、一気に仕入先の商品在庫を押さえ独占します。在庫を抑えた商品は、逆に値上げし利益確保を進めます。
さらにそのほかの広告の最適化や顧客対応、これら主要業務のほとんどを自動化するシステムを自ら開発・運用しました。私を含む3名で常時数万点の商品を扱い、億を超える売上を作り出しました。
しかし私がやっていたのはECショップ運営ではなく、薄利多売システムを作っていただけに過ぎませんでした。その時、自身のショップで何が売れているのかなどシステム任せだったので知りもしませんでしたし、その必要もない、とすら思っていました。
EC自動化の果てに失ってしまった「大切なもの」
売上も上がり、利益も出る。そしてその業務のほとんどは自動で回る。でも、「うん、最高!」とはなりませんでした。歪みはすぐに目に見えて現れました。
本来は高額である嗜好品であるブランド品を安売りしたことによって、顧客層のモラルレベルが圧倒的に下がりました。
具体例としては・・・
・代引きで注文しておいて受け取り拒否
・電話口でクチャクチャ物を食べながら命令口調、自分勝手なクレーム
・返品するために傷を付けて返す
などなど枚挙にいとまがありません。信じられないようなケースに多く接するようになり、対応するスタッフがどんどん病んでいきました。
スタッフは電話口では丁寧な対応を心がけていたのですが、ある日クレームの電話を切った瞬間、そのスタッフが今まで話していた電話口のお客さまについて悪態をつき始めました。その内に、社内での会話の多くが「今日はどんな酷いモラルのお客さんがいた」などと、最初は愚痴だったのがネタとして日常化していきました。
徹底的に数値管理してシステム化を追求することで、確かに売上も利益も上がりました。
しかし同時に、「商品に対する思い入れ」「仕入れの楽しさ」「自分たちのお店のカラー」「大切なお客さまとのコミュニケーション」、そして何よりも「ネットショップを運営する熱意」といった定量化できない大切なものを失ってしまっていたのです。
もちろん、喜んで利用いただいていたお客さまも多くいました。ただ、喜ばれる理由はその多くが価格でした。苦労して構築した究極的ローコストオペレーションだからこそ実現できたのですが、現実問題として、そのことはお客さまには通じません。
自動化もそうですが、本来価値ある商品を数値でしか見ず、正しい価値とサービスを正しい人に流通させなかったことで、社内がすさんでしまったりしたのですね。
得意分野の商品画像加工システムを商品化して取り返せたもの
それでも、食べるために自動化の道を突き進みました。
その中の1つが、現在弊社のメインサービスとなっている、商品画像加工の自動化システムであるZenFotomatic(ゼンフォトマティック)です。
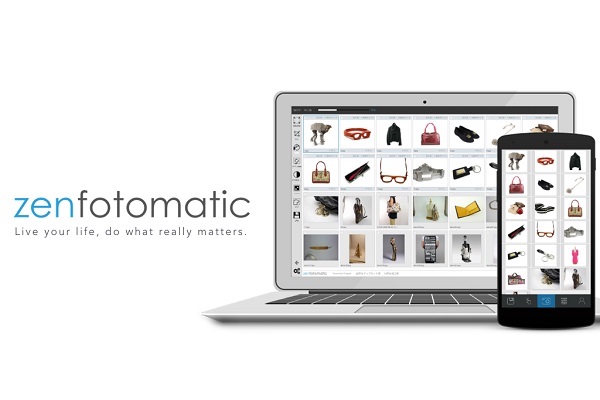
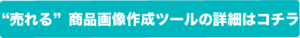
ネットショップは今も尚、高負荷で非効率な作業に満ちています。
各作業の時間やコストをを数値化した結果、中でもこの商品画像の加工作業に最もコストと時間がかかっていました。
さらに、商品画像は美しくシンプルであればその分アクセス(=来店)も売上もついてきます。
相当困難な開発になる事は目に見えていましたが、この自動化に取りかからない選択はありませんでした。
実際に自社の効率化ツールとして運用し始めてから、すぐに売上向上とコスト減の双方で効果が出ました。自社のツールとしてだけでなく、一般サービスとしてローンチしたところ国内外で多くの利用申し込みをいただく事ができました。
大変ありがたいことに、現在では個人利用から国内外の大企業まで約150カ国のネットショップでご利用いただいていますが、初期からの忘れられないお客さまがいらっしゃいます。
そのお客さまは、商品画像の加工を担当していた方が2名続けて鬱病にかかり急に辞めてしまい、毎晩遅くまで社長自身が一枚一枚画像加工をしていたそうです。
ある日、普段は見ない広告メールで偶然ZenFotomaticを見つけ、半信半疑で使ってみたところ、思わず叫び、涙してお喜びいただいたのだと伺いました。
ZenFotomaticは写真の中から自動的に被写体を認識して背景を切り抜き、白背景処理し、リサイズや余白調整、明暗補正などなど、実際に作業をしていたからこそ理解している複数の細かな必要作業をワンストップで盛り込んだシステムです。それを実現するために求められる技術はかなり高度なものです。
それが得意で熱意があるからこそ、困難な研究開発にのめり込むことができました。現在もそのモチベーションが失われることはありません。
餅は餅屋だと痛感しました。得意なことが人に喜ばれ、そして感謝と共にお金をお支払いいただけて、経済的にも心理的にもさらなる研究開発の糧となる。これが我々がすべき ”商い” だと心の底から腹落ちしました。
そしてその時には、自身もスタッフも熱を失っていたネットショップを閉じ、ZenFotomaticに集中することを決心しました。
あなたは、あなたが本来すべきことを!
冒頭から何度もくどいようですが、「数値管理」や「システム化」は避けて通れません。
実際、自動化できる業務はすぐにでも自動化すべきです。
しかしそれらはすべて、あなたの想いのこもった商品を、それに共感していただけるあなたのお客さまにお届けし、感謝と対価をいただくことで事業を継続させるためでしかなく、決して目的ではありません。
私は手段としてのシステムを、目的化してしまいネットショップ運営に失敗しました。一方で、得意なシステム開発を商品とし、それに集中することで小さくとも人様のお役に立つことが叶いました。あなたの商品は、あなただからこそ、それを求めている人に届けられるのです。
コンピューターの方が10倍早く処理でき、低コストでこなせる仕事を、あなたがやる理由はどこにもありません。それどころか、逆にあなたがすべきことをする大切で有限な時間を失っていることに等しいのです。
それは、限りある人生を無駄遣いしているとも言えます。
昨今では以前のようにシステムに何千万円も初期投資して自社開発する必要もなく、さまざまなシステムをインターネットを介しサービスとして利用するSaaSが一般化しており、導入のハードルは高くはありません。
前回のコラムでもお話ししましたが、あなたはあなたが本来すべき事をしましょう!
次回は・・・
皆さん、撮影した商品画像の管理はちゃんとできていますか?
商品画像もファイルデータです。これらをきちんとリネームして管理するだけで、商品登録作業の自動化も可能になり、さらに効率化できます。
ただし、リネーム作業も一ファイルずつタイピングで作業していては時間がかかるどころか往々にして人的ミスも多発します。
次回は、商品画像の管理に必要な画像ファイルのリネームを自動化する画期的な方法を、ZenFotomaticサポートチームの藤井に再度バトンタッチしてお送りします。
是非、ご期待ください!
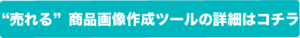
 三浦 大助 | グラムス株式会社 代表取締役 CEO
三浦 大助 | グラムス株式会社 代表取締役 CEO
アパレル商社で社内システム開発・保守に従事した後、2010年グラムス(株)を設立し、ネットショップ9店舗を立ち上げ運営。各種業務システムを自社開発した中から画像処理機能を「ZenFotomatic」としてローンチし、世界150カ国以上のネットショップに提供中。その他、EC系イベントで業務フローやシステム化などのセミナーで講師活動を行う。
▽連載一覧
第一回:「売れる商品画像」は思い込み?
第二回:1秒の効率化で大きく業務改善!
第三回:ECが構築すべき商品撮影環境とは?
第四回:超効率的な画像処理を実現するには?
第五回:商品撮影はスマホでOK!?その理由とは…
第六回:一眼レフは難しくない!業務改善も実現!?
第七回:1クリックで済む効率的な加工写真の作り方
第八回:ネットショップ店長がシステム屋になったワケ
第九回:ECに最適化された商品画像管理とは?
第十回:写真にこだわるECに潜む事業リスクとは?
第十一回:商品の色が写真と違う!を防ぐには?
第十二回:ついに最終回!世界で通用する商品画像とは?