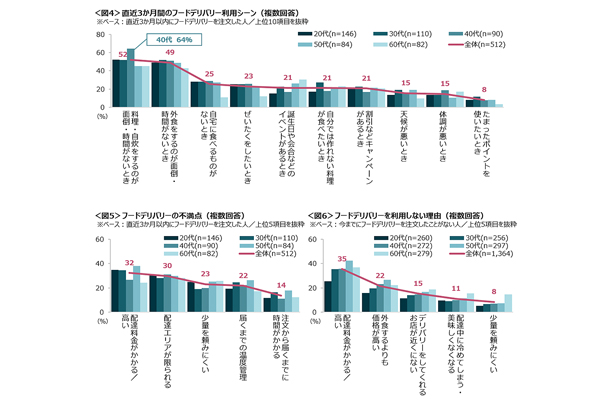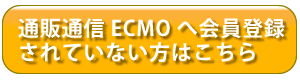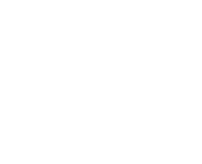2022.10.14 調査・統計
フードデリバリー、直近の利用率は20%…不満は「価格」「エリア」

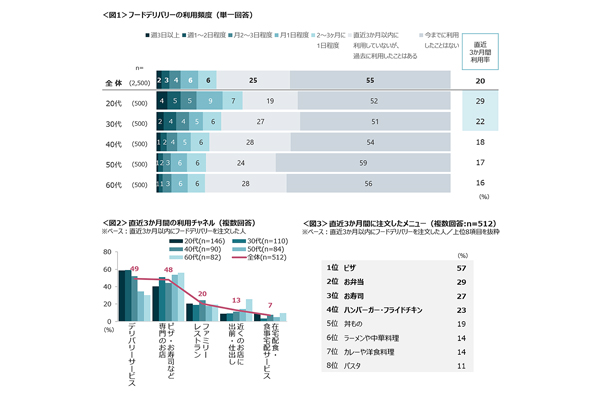
この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
機能性表示食品の基礎と落とし穴
-
2
オリジナル商品 Webデザインシミュレーター 『i-DESIGNER』
-
3
【生成AI×EC】EC運営でのAI活用方法
-
4
【AIタッガー】SEO×GEO AI検索時代の“見つかる力”を最大化
-
5
クロスセルを促進して顧客単価を向上!レコメンドサービス
ニュースランキング
-
1
【2月10日16時更新:物流配送状況】日本郵便/ヤマト運輸/佐川急便/西濃運輸/福山通運
-
2
「CBN」を指定薬物に、2月中旬に公布の予定…「販売」「使用」などは薬機法違反
-
3
東京ポイントの交換先に「PayPayポイント」「WAON POINT」を追加
-
4
メルカリ2Q、マーケットプレイス取引総額 前年同期比8.3%増の5994億円
-
5
dinos、芸人・歌手の石川晟也さんとコラボ第2弾…「母の日」キャンペーン実施